|
|
<2.星と太陽>
日時:平成16年2月20日(金)
場所:県立ぐんま天文台・少年科学館プラネタリウム
|
|

|
|
事前打ち合わせの様子。結城先生、岡崎先生をはじめ、PCDC学生スタッフと岡崎研究室の各メンバーが企画を練りました。
|
|
|
|

|
体験学習の場となる、県立ぐんま天文台へ下見にも行きました。
(まだ雪が残っていて寒かったぁ(>_<))
|
|
|
当日−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|

|
本番当日。太田市からブラジル学校ピタゴラスの生徒、伊勢崎市からペルー学校イスパーノ・アメリカーノ学院の生徒、合わせて約50人がスクールバスでやってきました。
午前の会場は、少年科学館プラネタリウム。北半球と南半球で星の見え方がことなることを学びます。
|
|
|

|
みんな、プラネタリウムはどうだった?
母国で見える星空と日本で見える星空の
違いを感じられたでしょうか?
|
|
|
|
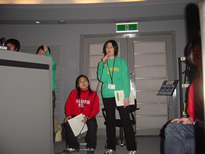
|
チーム「実行ボランティア」のルセロさん(右:工学部2年)とクラウジアさん(左:教育学部。県費留学生)。
スペイン語とポルトガル語の通訳で
サポートしました。
|
|
|
|

|
|
午後の会場となる、県立ぐんま天文台までバスで移動です。
|
|
|
|

|
|
ここからは徒歩。みんな行くよー♪
|
|
|
|

|
|
登り坂が続きます…しんどい…
|
|
|
|

|
残雪の山の風景を眺めながら、
天文台まで長い階段を登っていきます。
|
|
|
|

|
|
あ!見えた!ぐんま天文台に到着です。
|
|
|
|

|
|
残雪で雪合戦!
群大生も入り混じっての大合戦となりました。
|
|
|
|

|
北半球と南半球それぞれから見える
太陽の動きについて岡崎先生がお話して
くださいました。
|
|
|
|

|
今回の事業で大活躍だった岡崎研究室
チーム「OKstars」のみなさん。
|
|
|
|

|
子どもたちに少しでもわかりやすく
説明しようと学生たちも奮闘。
|
|
|
|

|
|
みんなが真剣に作っているのは…
|
|
|
|

|
日時計!!画用紙とストローを使って
上手にできました。
|
|
|
|

|
|
さっそく外に出て、日時計を使ってみます。
|
|
|
|

|
日時計は影の差す位置によって時間を
知ることのできる時計。
今の時間は?
|
|
|

|
室内に戻って、施設内の展示物を
見学しました。
|
|
|
|

|
観測装置の仕組みや観測データの解析など天文台の仕事が模型やCGなどで
わかりやすく解説されています。
|
|
|
|

|
なかでも巨大な望遠鏡には圧倒されました。写真は65cm反射望遠鏡。
65cmは、最初に光が当る鏡の直径の長さを示しています。
|
|
|
|

|
この反射式望遠鏡は、レンズは使わず、
凹面鏡と凸面鏡を組合せて光を集めています。みんな興味津々でした。
|
|
|
|

|
青空をバックにみんなで記念撮影。
ブラジル学校とペルー学校の子どもたちと交流しながら、北半球と南半球の星と太陽の動きの違いを
楽しく学べました。
|
|
|